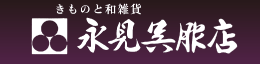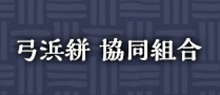~弓浜絣~ 鳥取県西部の弓ヶ浜地方では、江戸時代前期に砂地を利用した綿の生産が始まりまし た。繊維が細くて強く、保湿性と弾力性に富む良質の「伯州綿」を手引き糸にして利用 しました。 1975年に国の伝統的工芸品に、1978年には県指定無形文化財に指定されました。 弾力が特徴の伯州綿は、手紡ぎされて膨らみのある糸となり絣模様に藍染めされた後、高機で織られて一枚の布となります。 鶴亀や松竹梅などの吉祥模様のほか、風景、動物、幾何模様、物語や時代背景など限りなく、飾らぬ表情で人の想いと時代の流れを伝えます。 古い木綿絣に心動かされ、手が生む布の風合いに惹かれて、綿、糸、染め、織りそれぞれに浜に伝わる手作業で仕事をしています。 |
弓浜絣の織り上がるまで
 |
||||
|
①伯州綿 地元の弓ヶ浜半島で育った弾力のある伯州綿(浜綿)を使います。 |
②綿繰り 綿から中の種を外します。その後綿の繊維をほぐす綿打ち作業をします。 |
③糸紡ぎ 糸繰り機で綿を撚りを掛けながら一本の糸にしていきます。熟練のいる作業です。 |
 |
||||
|
④絣糸括り 絵絣を生み出すための作業、麻糸(現在は主にビニール紐)を使って防染します |
⑤藍染め 好みの藍色を出すために何回も甕につけて染めます。 |
⑥織り 昔ながらの高機で絣の柄を合わせながら丁寧に織り上げていきます。 |